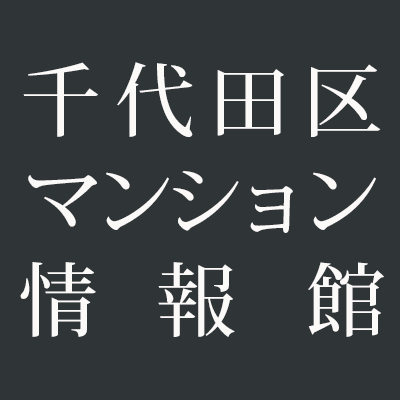経営陣が自社株を買い取り、
ファンドと共に非公開化する動きが急増中
2025年現在、**企業の上場廃止=MBO(マネジメント・バイアウト)**が再び注目を集めています。
経営陣が自社株を買い取り、ファンドと共に非公開化する動きが急増中。
その背景には「株主の干渉から離れ、自由な経営を目指す」という理想がありますが、果たしてその狙いはどこまで実現されているのでしょうか?
この記事では、日本経済新聞の最新報道をもとに、MBO企業の再上場後の実態を読み解きながら、富裕層にとっての資産運用や不動産投資へのヒントを考察していきます。
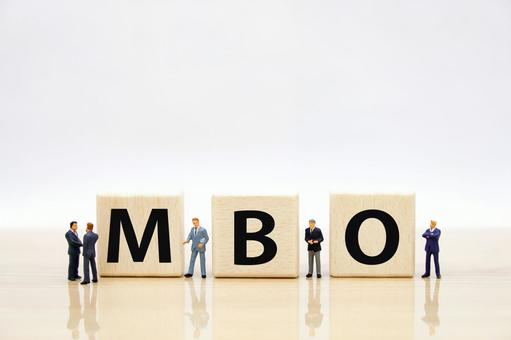
MBOとは何か? そしてなぜ増えているのか?
MBOとは「マネジメント・バイアウト」の略で、経営陣自らが自社株を買い取り、上場を廃止する手法です。
近年では上場企業に対する株主の要求が強まる一方で、東京証券取引所の上場基準の厳格化もあり、自由な経営を求める中小〜中堅企業がMBOに踏み切るケースが増加しています。
M&Aアドバイザリー大手レコフによれば、2020年〜2024年の5年間で、MBOによる上場廃止は77件にも達しました。
ROEが改善…でも実は「借金マジック」?
非公開化後、再上場した企業の多くは、財務指標の代表格である**ROE(自己資本利益率)**が劇的に改善しているように見えます。
例えば、同志社大学の野瀬義明教授の分析によれば、再上場企業18社の平均ROEは、
MBO前の7.6% → 再上場後は14.2%へとほぼ倍増。
これは一見すると「MBOによって企業体質が改善された」ように見えますが、実は裏があります。
→ 改善の正体は「財務レバレッジ」
ROEは以下の3要素に分解できます:
- 売上高純利益率(利益の出やすさ)
- 総資産回転率(資産の効率性)
- 財務レバレッジ(借金のテコ)
この中で、MBO企業のROE上昇は財務レバレッジ=借金の力によるものが大半。
企業が借金を増やし、自己資本を圧縮することで、利益がさほど変わらなくても**“ROEだけ”は跳ね上がる**のです。
まさに“数字のマジック”とも言える現象です。
MBO後の企業改革は「成長」とは限らない
もちろんMBOには再建の意図もありますし、成功事例も存在します。
たとえば、金属加工大手「トーカロ」は、MBO後に半導体分野に特化して成長し、時価総額をMBO前の24倍にまで増やしました。
一方で、「スシロー」「ワールド」「すかいらーく」など、再上場までに10年以上かかり、再建に苦労した例も少なくありません。

投資家にとってのリスクと“出口”の問題
ファンドの投資期間はおおむね4〜5年が一般的。その間に利益を上げ、再上場または売却によって「出口」を迎える必要があります。
このプレッシャーの中で、成長投資は先送りされがち。
「利益の数字は整ったが、持続的な成長基盤が整っていない」
というケースも多く、長期目線の投資家にとっては注意が必要です。
実際、MBOによって再上場した13社を比較すると、再上場1年後の時価総額は2.9倍になっていたものの、4年後にはTOPIXと同等レベルに失速しているというデータもあります。
富裕層が考えるべき「MBO × 不動産」の視点
MBOは企業経営にとっての一大イベントですが、富裕層の資産形成においても他人事ではありません。
例えば、以下のようなケースが考えられます:
- 再上場を目指すMBO企業に「個人投資家」として出資する
- MBOで非公開化された企業が所有する不動産を割安で取得
- 経営者と連携し、物件や資産を切り離して活用
特に千代田区のような高級オフィスや商業ビルが多いエリアでは、MBOによって動く企業不動産の売買も起こりやすく、
目利きのある富裕層にとってはチャンスと捉えることもできます。

「ROE」だけを見てはいけない時代へ
数字上は優秀でも、実態は借金頼み。
そんなMBO企業が増える中で、私たち投資家や資産家は、“財務指標の裏側”を見る力が問われています。
- 数字の裏にある成長戦略はあるか?
- 経営陣は本当に自由を手に入れているのか?
- ファンドと企業の関係性は良好か?
これらを精査しない限り、“甘いワナ”に引き込まれてしまうリスクがあります。
まとめ|MBOを「チャンス」と捉えるか、「落とし穴」と見るかは自分次第
「非上場化=自由な経営=成長加速」というシンプルな構図が通用しない今。
数字の上でROEが高くても、本質的な成長を伴わない企業に投資してもリターンは限定的です。
とはいえ、MBOは資産再編や事業承継の起点にもなり得ます。
特に、千代田区のような優良不動産を抱えるエリアでは、MBOをきっかけに資産価値が再評価されるケースもあるでしょう。
📞 ご相談はお気軽にどうぞ
資産運用、不動産戦略、M&Aや企業再編に関心のある方へ。
千代田区マンション情報館では、実務経験豊富なコンサルタントが個別相談を承っております。
📞 ご相談窓口
株式会社MIRABELL(ミラベル) 担当:小川
TEL:03-3261-5815
携帯:080-6794-3089
✉️ メール:ogawa@mirabell.co.jp
千代田区マンション情報館
株式会社MIRABELL 担当:小川
電話:03-3261-5815
携帯;080-6794-3089
メールアドレス:ogawa@mirabell.co.jp