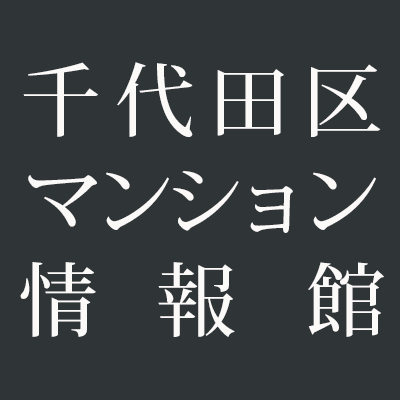次世代の資産設計をどう考えるべきかを深掘りしていきます
「親の資産がまったく減っていない」
「何不自由なく暮らしているのに、手を付けない預金がある」
──これは、実はよくあるご相談の一つです。
2025年3月28日付の日経新聞では、「なぜ高齢者は資産を取り崩さないのか?」という疑問に切り込みました。
富裕層の皆さまが資産を“使わない”ことには、明確な戦略と哲学があります。今回はその背景と、**「遺産動機」と「予備的貯蓄」**というキーワードを軸に、次世代の資産設計をどう考えるべきかを深掘りしていきます。

「遺産動機」とは何か?
遺産動機とは、文字通り「資産を残したいという気持ち」のこと。
子や孫に何かを遺したいという思いがあれば、当然ながら手元資産を簡単には取り崩さない。
逆に「自分が楽しむために使い切る」と考える人には、遺産動機はありません。
とくに日本の富裕層に多いのが、「使わずに残すことで、次世代への責任を果たす」というスタンスです。

もう一つの理由──「予備的貯蓄」という安心装置
高齢期に資産を残すもう一つの理由が、「万が一に備える」ための貯蓄です。
これを経済学では「予備的貯蓄(Precautionary Saving)」と呼びます。
具体的には──
- 予想より長生きした場合の生活費
- 医療・介護にかかる予想外の費用
- パートナーが先に亡くなった後の一人分の暮らし
など、「いつか起きるかもしれない事態」に備える貯蓄です。
この貯蓄が不要だった場合、結果としてそれが“遺産”となって子や孫に残る、というわけです。
アメリカの事例に学ぶ「取り崩さない高齢者」の行動
米バージニア大学のロックウッド教授の研究では、アメリカでも同様の現象が確認されています。
ポイントはここ:
「民間介護保険に入らなくても、高額な予備的貯蓄があれば対応できる」
この心理が働くことで、高齢者はますます資産を取り崩さなくなります。
そして「もし使わずに済めば、その分は子どもや孫の未来資金になる」という遺産動機と結びつきます。
つまり、“取り崩さない=損しない=遺せる”という選択が合理的になっているのです。
では、相続は格差を広げるのか?
こうした資産の蓄積が子世代に引き継がれるとき、よく言われるのが「格差が固定化されるのではないか?」という議論です。
これは確かに一面の真実ではあります。
しかし、記事でも指摘されている通り──
- 親があえて遺産を残さない場合(教育機会は提供済み、あとは自力で)
- 子の労働意欲や資産形成意識を育てたいと考える親世代
このようなケースでは、「資産はあるが、相続はコントロールしている」家庭も少なくありません。
相続による格差の“固定”は、単に資産があるかどうかではなく、どう渡すか、いつ渡すか、何を渡すかが鍵なのです。

富裕層が実践すべき「資産を使わずに伝える」戦略
千代田区マンション情報館の読者である皆さまにとって、「資産を守る」「育てる」ことはライフワークの一部かもしれません。
では、それをどう“渡すか”?
以下のような戦略が、今後ますます重要になってきます。
① 収益性のある資産を残す(現金よりも不動産・株式)
不動産や株式といった“働く資産”は、次世代にとっても「学び」と「収益」をもたらします。
- 賃貸マンション:毎月の家賃収入
- 都心オフィスビル:法人活用で節税+相続対策
- 配当株ポートフォリオ:金融教育の教材にも
② 「使わせる」のではなく「関わらせる」
相続=財産の譲渡ではなく、「資産と付き合う体験の相続」と考えましょう。
- 物件の管理を子どもに一部任せる
- 決算書を一緒に見る
- 法人役員に就けて、税理士と話す機会を作る
③ 介護・医療費リスクを可視化し、「遺す前提」で設計
予備的貯蓄の重要性を踏まえ、
- 介護施設費用の概算
- 医療保険・民間介護保険のプラン
- 生活費のキャッシュフロー表
を“見える化”することで、資産を取り崩さずに済む準備を整えることが可能になります。
まとめ|「使わない選択」は、未来への布石
資産は使うためにある──
その通りです。でも、「使わずに残すこともまた、戦略的な選択」であることは間違いありません。
遺産動機は、単に感情的な親心ではなく、**“見えない資産防衛の仕組み”**でもあります。
富裕層だからこそ選べる「使わない」という選択。
その背後には、次世代に向けた深いメッセージが込められているのです。
📞 相続を見据えた不動産活用・資産設計はご相談ください
千代田区マンション情報館では、収益不動産・法人活用・相続対策に関するサポートを承っています。
「取り崩さずに遺す」「資産を使わずに育てる」戦略を一緒に設計しませんか?
📞 ご相談窓口
株式会社MIRABELL(ミラベル) 担当:小川
TEL:03-3261-5815
携帯:080-6794-3089
✉️ メール:ogawa@mirabell.co.jp
千代田区マンション情報館
株式会社MIRABELL 担当:小川
電話:03-3261-5815
携帯;080-6794-3089
メールアドレス:ogawa@mirabell.co.jp